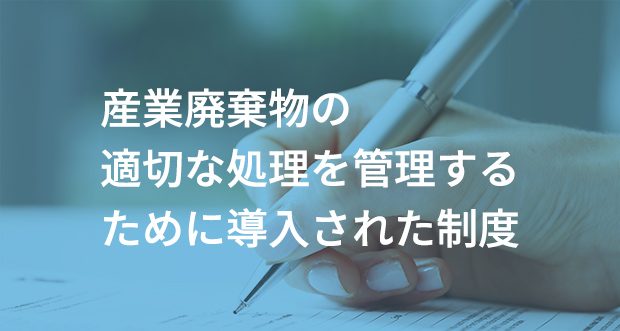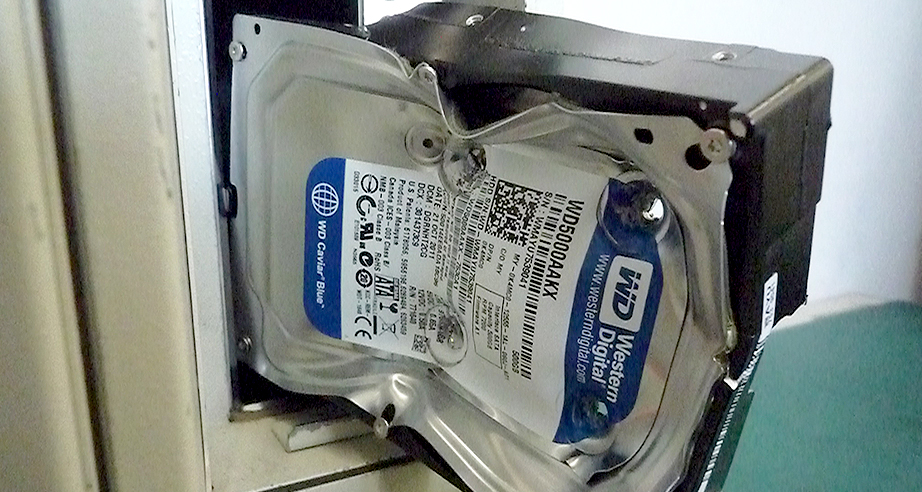電子マニフェストとは?
導入の流れと運用について
電子マニフェスト導入で業務負荷軽減
導入のメリットや活用事例、導入の流れについてご紹介
1. 電子マニフェストとは?その必要性とメリット
電子マニフェストの必要性

電子マニフェストは、産業廃棄物の管理を効率化する電子システムです。排出事業者、収集運搬業者、処分業者がリアルタイムで情報を共有し、廃棄物処理の全過程を一元的に管理します。電子マニフェストシステムは、1970年に制定された「廃棄物処理法」に基づき、日本産業廃棄物処理振興センター(JWN)が提供しており、その結果、従来の紙ベースのマニフェストに代わり、インターネットを活用して廃棄物の処理状況を記録・確認できるようになりました。電子マニフェストは、事業者にとって業務負担の軽減と管理の透明性向上を目的とした重要なツールです。
近年、環境保全や持続可能な社会の実現に向けた取り組みが進む中、産業廃棄物の適正な処理が社会的に重要視されています。廃棄物の不適切な処理は、環境汚染や社会的信用の低下、さらには法令違反につながるリスクを伴います。このような背景から、電子マニフェストは、廃棄物管理の透明性を確保し、不正や誤りを防ぐための仕組みとして必要性が高まっています。
また、廃棄物処理法の改正や規制強化に伴い、事業者にはより厳格な管理体制が求められるようになりました。紙ベースのマニフェストでは、手作業での記録や確認が必要で、多大な時間と手間がかかる上、人的ミスが起こりやすいという課題がありました。電子マニフェストはこうした課題を解決し、効率的かつ正確な廃棄物管理を実現する手段として、多くの事業者に注目されています。
さらに、競争力を維持するためには、業務効率の向上が欠かせません。電子マニフェストを導入することで、廃棄物の処理状況をリアルタイムで確認でき、データを一元管理することが可能になります。これにより、紙書類の保管スペースや不要な手続きが削減され、迅速で正確な意思決定が可能になります。このシステムは、廃棄物管理業務全体の生産性を向上させるだけでなく、環境保全やコンプライアンスの強化も促進します。
こうしたことから、電子マニフェストの導入は、環境保全や法令遵守、さらには企業の持続的な成長を支える上で、今や不可欠なツールと言えるでしょう。
電子マニフェストのメリット
電子マニフェストの導入には、多くの具体的なメリットがあります。以下に主な利点をご紹介します。
1. 管理の効率化
電子マニフェストを導入することで、従来の紙ベースで行われていた煩雑な書類のやり取りが不要になります。廃棄物に関するデータはすべてオンライン上で、一元管理されるため、担当者間の連絡ミスや手続き上の遅延を防ぎます。また、リアルタイムで進捗状況を確認できるため、業務のスピードアップと効率化も実現します。行政への報告業務も自動化されるため、事務負担の軽減にもつながり、全体的な管理精度を高めることが可能です。
2. トレーサビリティの強化
電子マニフェストでは、廃棄物の排出から収集運搬、最終処分までの全ての流れをリアルタイムで追跡し、記録することができます。この透明性の高い仕組みにより、産業廃棄物の処理が最終工程まで正しく行われたかを確認・記録でき、管理体制の信頼性が向上します。また、電子マニフェストを介すると、処理業者間での確認作業もスムーズに行えるため、業務全体の安全性が強化され、事業者のリスク軽減にも貢献します。
3. データ分析と最適化
電子マニフェストでは、廃棄物の発生状況や処理状況に関する詳細なデータを蓄積することができます。このデータを活用することで、どの事業所からどのような廃棄物がどれだけ排出されているのかなどを調査・把握し、現状の廃棄物管理体制を可視化することが容易になります。その上で、排出量削減やリサイクル率向上を含めた、廃棄処理コストの削減を目指して、最適な廃棄物処理計画の立案に役立てることが可能となります。
4. 環境負荷の軽減
電子マニフェストの導入により、紙ベースのマニフェストが不要となるため、紙資源の使用量を大幅に削減できます。これにより、森林資源の保全に貢献するとともに、紙書類の保管スペースも不要になるため、オフィス内のスペース効率も向上します。また、適切な廃棄物処理を促進し、不正処理を防ぐことで、環境汚染やエコシステムへの影響を最小限に抑えることが可能です。電子マニフェストは、環境保全の一環としても大きな役割を果たします。
5. 法令遵守の確実性
電子マニフェストは、廃棄物処理に関する必要な記録や行政への報告を自動化する機能を備えています。この仕組みにより、提出期限の漏れや記録ミスといった人的なエラーを防ぎ、法令遵守を確実に実現することが可能です。また、監査時に必要なデータを迅速に提示できるため、コンプライアンス対応の負担が軽減されます。電子マニフェストを利用することで、事業者は安心して運用を続けることができ、社会的な信頼性を高めることができます。
電子マニフェストの導入は、廃棄物管理業務の効率化、トレーサビリティの強化、データ分析による最適化、環境負荷の軽減、そして法令遵守の確実性といった多岐にわたるメリットをもたらします。これらのメリットにより、企業は持続可能なビジネス運営を実現し、社会的責任を果たすことが可能となります。
2. 従来の紙マニフェストと電子マニフェストの比較
電子マニフェストのメリットをより具体的に理解するために、ここでは従来の紙マニフェストとの主な4つの違いを挙げて比較します。この比較を通じて、電子マニフェストが企業の廃棄物管理にどのような利便性をもたらすのかを明らかにします。
マニフェスト運用プロセスの違い
紙マニフェスト
廃棄物の引き渡し時に手作業で記入された紙の伝票を交付し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の間で受け渡されます。各工程の進捗を確認するためには、関係者が個別にマニフェスト伝票を確認する必要があり、ミスや紛失のリスクが高い点が課題となります。
電子マニフェスト
インターネットを利用して、廃棄物の排出から最終処分までの状況をオンライン上で記録・管理します。情報はリアルタイムで共有されるため、電子マニフェストは進捗状況を簡単に確認でき、紙のやり取りが不要となります。
マニフェストの作業負担の違い
紙マニフェスト
マニフェスト書類の用意から記入や交付、保管が必要で、手作業が中心となるため業務負担が大きくなります。特に、大量の廃棄物を扱う事業者では、運用コストが増加します。
電子マニフェスト
手作業が不要になり、情報の登録や確認はオンライン上で完結します。電子マニフェストはデジタル入力を前提としているため、事務作業の効率化が図れるだけでなく、必須項目の未記入や記載内容の矛盾をシステムで自動的にチェックできるので記録のミスや記載漏れのリスクも軽減されます。
マニフェストの保管と情報アクセス性の違い
紙マニフェスト
各伝票を事業者が5年間保管する義務がありますが、物理的な保管スペースが必要となり、管理コストが発生します。加えて、マニフェスト用紙による管理は、必要な情報を検索するのに手間がかかります。
電子マニフェスト
データは「JWNET」に5年間保存されるため、事業者が個別に保管スペースを確保する必要がありません。また、必要な情報を迅速に検索・確認できるため、管理が簡素化されます。
トレーサビリティと透明性の違い
紙マニフェスト
廃棄物の進捗状況を確認するためには、関係者が伝票を手作業で照合する必要があり、透明性や迅速性が制限されます。不適切処理や紛失が発生した場合、その特定に時間がかかることがあります。
電子マニフェスト
廃棄物の処理状況をリアルタイムで確認できるため、トレーサビリティが強化されます。全体の流れを可視化することで、問題の早期発見や迅速な対応が可能になります。
環境負荷の違い
紙マニフェスト
大量の紙を使用するため、環境負荷が高いとされます。また、書類の移動や保管にエネルギーを要し、持続可能性の観点から課題があります。
電子マニフェスト
完全な電子化により紙資源の使用が不要となり、環境保護に寄与します。また、物理的な移動がないため、関連するエネルギー消費も削減されます。
従来の紙マニフェストは、廃棄物管理の基本的なツールとして長年利用されてきましたが、手間やコスト、透明性の面で課題がありました。一方、電子マニフェストは、こうした課題を解消し、効率的で透明性の高い廃棄物管理を実現します。そのため、企業の業務負担を軽減し、環境保護や法令遵守を支えるための効果的な選択肢として注目されています。なお、運用に際しての「紙マニフェストと電子マニフェストの比較」については、こちらのページでも解説しています。
3. 電子マニフェストを活用した成功事例
電子マニフェストを導入すると、企業はどのようなメリットを得られるのでしょうか?ここでは、大手ネット通販会社L社様の導入事例を通して、電子マニフェストがもたらす具体的な効果を見ていきましょう。
年間数千枚に及ぶ紙マニフェスト作業の多大な工数と作業費を削減
大手ネット通販会社L社様

L社様は、家具の販売・納品時に購入者から引き取る不要品(家具)の産業廃棄物処理において、従来は紙ベースのマニフェストを使用していました。年間数千枚に及ぶ紙マニフェストの照合や「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の作成には、多大な人手と時間が必要であり、運用コストの増大が課題となっていました。
この課題を解決するため、L社様はSBS即配サポートの提案により、紙マニフェストから電子マニフェストへの切り替えを実施しました。これによって、L社様、収集・運搬会社、処分事業者間で情報をオンライン上で共有・管理する体制を構築しました。
電子マニフェストの導入により、L社様の国内全拠点で得られた効果は以下の通りです。
-
事前予約登録の活用
集積場所から処理施設までの運搬や処理内容を事前に予約登録できるようになり、業務の効率化が進んだ。
-
迅速な報告体制の構築
収集・運搬会社は、電子マニフェストシステムを通じて各集積拠点の情報を呼び出し、短時間で「収集運搬終了報告」を行えるようになった。
-
照合作業の削減
紙マニフェストで必要だった各工程の帳票照合が不要となり、処理状況をリアルタイムで把握できるようになった。
-
報告書作成の省略
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成が不要となり、法的に義務付けられている紙マニフェストの長期保管(5年間)も不要となった。
これらの結果、L社様は運用コストの大幅な削減に成功しました。電子マニフェストの導入が廃棄物管理の効率化とコスト削減に大きく寄与することが実証された事例と言えます。詳細な情報や他の事例については、こちらの電子マニフェスト運用事例をご覧ください。
4. 電子マニフェスト導入の流れと運用
電子マニフェストを導入する際には、どのような手続きや準備が必要になるのでしょうか?また、導入後にはどのように運用していくべきでしょうか?ここでは、当社のサポートの下、廃棄物排出事業者様が電子マニフェストの導入を進める際に必要な対応内容や、導入後の運用で押さえておくべきポイントについてご説明します。導入の流れをスムーズにするための主なステップや作業内容を整理するとともに、運用時に知っておくべき基本事項を分かりやすくお伝えします。
〔1〕電子マニフェストの導入手続きについて
電子マニフェストを導入する場合、まずは「JWNET(日本産業廃棄物処理振興センター)」に加入する必要があります。お申込みはWEBサイトから可能です。詳細はJWNETのサイトをご覧いただければと思いますが、ここではポイントをまとめておきます。
-
電子マニフェストを導入する場合、JWNETに加入する必要があります。
-
加入申込の方法についての操作方法はYouTubeにて説明があります。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/manual/guide/movie/moushikomi.html
JWNETの料金区分は、マニフェストの年間登録件数などに応じて選択できます。【料金区分】https://www.jwnet.or.jp/jwnet/youshiki/payment/fee/
【利用料金シミュレーション】https://www.jwnet.or.jp/jwnet/youshiki/payment/plan-select/
-
JWNETへはWEBサイトから申込可。仮申込後、本登録を行います。
【JWNET仮申込フォーム】
https://www.jwnetweb.jp/p/wusr/000032/application/html/user/pre_register/index.html#input -
仮申込に必要なユーザー情報は、「事務担当者名」と「メールアドレス」です。
-
本登録で利用するURLは、仮申込時に入力したメールアドレスに届きます。本登録時に必要な排出事業者の情報は「料金区分/業種/組織種別(株式会社など)/加入者名/代表者名/TEL/加入者情報公開の可否/料金支払い方法(口座振替など)」です。
-
上記申込後、当日中に“加入手続き完了メール”が届きます。そこに「加入者番号」の記載があります。
【加入者番号の管理画面上での調べ方】
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/faq/Q3-422.html -
「EDI利用確認キー」の管理画面上での確認方法は
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/faq/Q3-167.html
にあります。 -
当社には、「加入者番号」と「EDI利用確認キー」をお知らせいただく事で、電子マニフェストの作成代行が可能となります。
-
排出事業者は排出事業者ごと、もしくは排出事業場を管轄する本社や支店等の単位での加入など、「加入の単位」選択は自由です。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/practice/flow/member/-
一元管理が可能/加入費が纏められる → 統括部門での加入
-
排出部門毎での排出量が把握できる/各部門で対応できる → 排出事業場ごと
-
〔2〕 電子マニフェストの運用について
SBS即配サポートでは、産業廃棄物の処理を委託いただく際に、電子マニフェストの運用をスムーズに進めるためのサポート体制を整えています。ご契約書を交わした後に上記導入手続きでご用意頂いた「加入者番号」と「EDI利用確認キー」を当社にお知らせいただければ、「bee-netシステム」(株式会社ビートルマネージメントが提供するASPサービス)を活用して、当社が電子マニフェスト作成を代行いたします。以下では、その一般的な流れをご紹介します。
-
電子マニフェストの作成
廃棄物を処理する際に、ご契約書を交わしますので、これに基づいて当社が電子マニフェストを「bee-netシステム」を活用して登録します。
(排出事業場、廃棄物の種類、収集運搬先(積替保管先)、処分場の場所、処分方法など) -
JWNETシステムへの登録
上記により、マニフェストの内容がJWNETシステムに反映されますので、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者がオンライン上で情報を共有し、廃棄物の処理過程を確認することができます。
-
廃棄物の収集・運搬
収集運搬業者が排出事業場所に訪問し、廃棄物を収集します。収集運搬業者は、廃棄物の運搬完了日や運搬担当者、収集量など、運搬の実績を入力します。
-
処分業者による処分完了と報告
処分業者が廃棄物の受け入れを行い、処分を実施。処分後は、処分完了日/処分量などを入力します。
-
排出事業者への通知
収集運搬業者や処分業者からの完了報告をもとに、排出事業者は廃棄物処理における工程をマニフェストにて確認します。
-
実績データの管理
排出事業者はマニフェストをシステムにて一元管理できます。廃棄物処理法に基づく行政への報告(交付等状況報告書)はJWNET(日本産業廃棄物処理振興センター)が都道府県知事等に報告を行いますので、排出事業者が自ら報告する必要はありません。また、JWNETシステムより実績データをダウンロードできますので、必要に応じて実績書類等の作成に活用することが出来ます。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/system/report/
5. 電子マニフェスト導入でよくあるご質問と回答
電子マニフェストの導入を検討される際、多くの事業者様からさまざまなご質問をいただいております。ここでは、導入や運用に関してよく寄せられるご質問を挙げ、その回答を掲載しました。初めて電子マニフェストをご利用になる方や、運用に不安をお持ちの方も、ぜひご参考になさってください。
なお、JWNETで直接申請するだけでなく、電子マニフェスト運用に便利なEDIサポートシステムをご利用になる場合は、別途利用料が必要になることもあります。そちらはご契約先の料金に準じます。なお当社のサポートの下で電子マニフェストを運用頂く場合は、当社が導入している「bee-netシステム」(株式会社ビートルマネージメントが提供するASPサービス)を利用しての運用となります。この場合「bee-netシステム」システムの利用料は特に必要ありません。産業廃棄物の処理を当社にご依頼頂ける場合は、「bee-netシステム」を利用した電子マニフェストの作成代行、電子マニフェスト導入や導入後の運用面についてのサポートが可能です。
当社による電子マニフェストの作成代行をご希望の場合は、「JWNET」に加入頂いた後、「加入者番号」と「EDI利用確認キー」を当社にお知らせいただければ、「bee-netシステム」へのEDI接続設定を当社にて行います。「加入者番号」と「EDI利用確認キー」をお知らせ頂いた後、約3営業日より運用開始が可能となります。